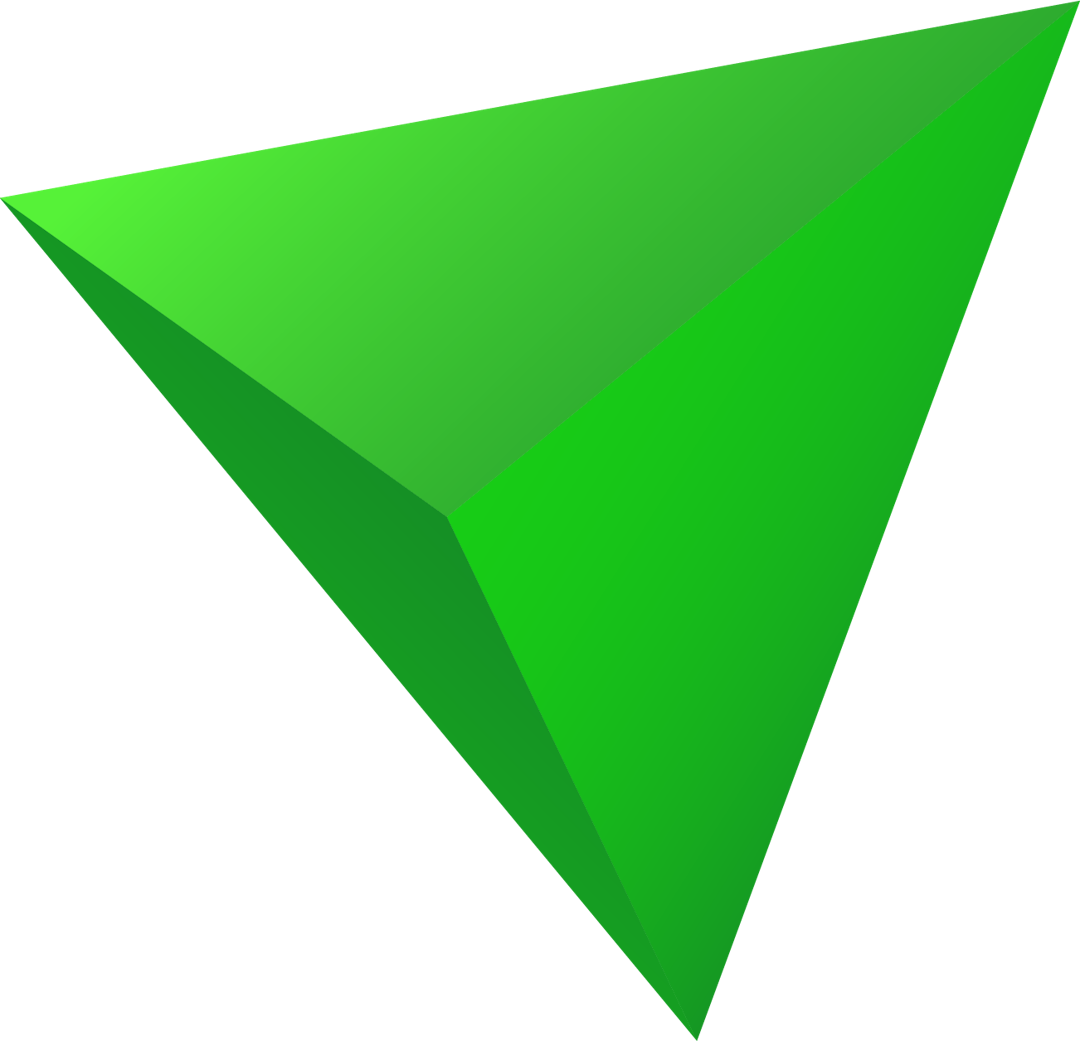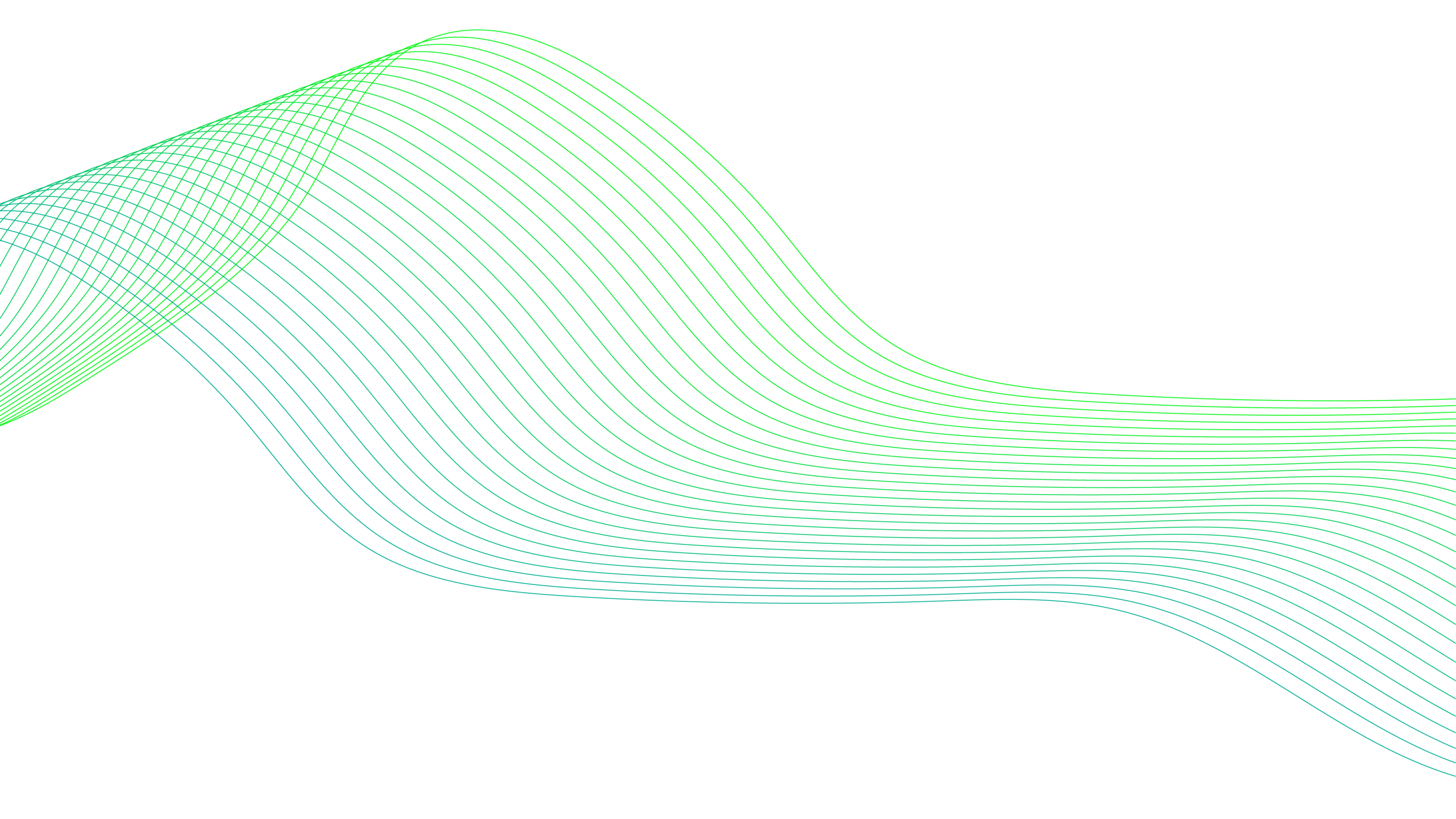
第1章 総則
- 第1条(名称)
本組織は日本パーラメンタリーディベート連盟と称する。英語ではJapan Parliamentary Debate Unionと表示し、略称をJPDUとする。
- 第2条(目的)
本組織は次に掲げる目的のために活動を行う。
1. 国内の英語パーラメンタリーディベート活動関係者のネットワークの構築
2. 情報提供、イベント開催、教育活動その他の活動を通じた英語パーラメンタリーディベート活動の普及と環境の向上
3. 国際ネットワークの構築を通じた英語パーラメンタリーディベート環境の向上
- 第3条(活動)
本組織は次に掲げる活動を行う。
1. 日本英語パーラメンタリーディベート界全体としての意思決定
2. ディベートトーナメントの開催
3. ワークショップ、セミナーの開催
4. 英語パーラメンタリーディベートの普及に関する各種活動
5. JPDU Equity Policyの推進
6. 英語パーラメンタリーディベート活動を支援するインターネットサービスの提供
7. 大会記録や資料の蓄積
8. 他団体との交流・協力
9. 前各号に掲げるもののほか、前条の目的に合致すると認められるその他の活動
第2章 会員
- 第4条(会員の定義)
本規約においては、次に掲げる者を合わせて「会員」と称する。
1. 通常会員(加盟団体の構成員をいう。)
2. 個人会員(日本の大学またはこれに準ずる教育機関(以下「大学等」という。)に所属しているが、自身の所属する教育機関に加盟団体が存在しない場合において、本組織へ入会している個人をいう。)
- 第5条(加盟団体の資格)
1
英語パーラメンタリーディベート活動を行っているまたはこれから始めようとしている日本の大学等の学生団体は、本組織の加盟団体となる資格を有する。
2
加盟団体は、当該大学等の構成員のみによって構成されなければならない。ただし、所属している大学等における活動人数が著しく少ないその他やむを得ない事情があり、加盟団体としての承認を受けるときに、代表による承認を受けた場合はこの限りでない。
- 第6条(会員の資格)
本組織の会員となる資格は、次に掲げる者が有する。
1. 前条に規定する団体の構成員。
2. 日本の大学等に所属しているが、自身の所属する教育機関に加盟団体が存在しない場合の個人。ただし、当該人物が所属する学生団体が加盟団体となった場合は、当該人物は個人会員の資格を失う。
- 第7条(入会)
1
本組織への入会期間は毎年4月1日から翌年3月31日を期限とする1年間とし、年度途中での入会を行った場合でも3月31日を期限とする。
2
第5条に規定する団体が次に掲げるいずれかの条件を満たし、代表の承認を受けたときは、当該団体は加盟団体として承認される。ただし、代表は正当な理由がなければ承認を拒むことができない。
1. 第5章に規定される役員選挙(以下「役員選挙」という。)の実施時に、選挙への参加の意思を示したとき。ただし、前年度に加盟団体であった団体に限る。
2. メールその他適当な方法によって、代表に対して加盟団体としての承認を受けることを希望する意思を示したとき。
3
第5条に規定する団体が加盟団体として承認されたときに、当該団体の構成員は、本組織の通常会員となる。
4
前条第1項第2号に該当する者は、メールその他適当な方法によって、代表に対して個人会員としての承認を受けることを希望する意思を示し、代表の承認を受けたときは、個人会員として承認される。ただし、代表は正当な理由がなければ承認を拒むことができない。
- 第8条(退会)
1
加盟団体または個人会員が年度途中にやむを得ない事情をもって本組織から退会するためには、退会を希望する旨をメールその他適当な方法で代表に申請し、JPDU議会において第26条の方法(以下「特別多数決」という。)による承認を受けなければならない。
2
加盟団体が退会した場合においては、その団体の構成員は通常会員の地位を失う。個人会員の地位を得るためには、前条第4項の方法による承認を受けなければならない。
3
通常会員が加盟団体から退会したときは、本組織から退会したものとみなす。
4
加盟団体または個人会員が退会した場合においても、加盟団体及び会員は第9条及び第10条に定める義務を当該年度内に継続して負う。ただし、やむを得ない事情があるとJPDU議会が認めたときは、この限りでない。
- 第9条(会員の義務)
本組織の会員は次に掲げる義務を負う。
1. JPDU Equity Policyの遵守。
2. 年会費の納入。ただし、JPDU会費納入規則に定める一定の要件を満たすときは、その義務を免れる。
- 第10条(加盟団体の義務)
1
役員選挙の立候補期間終了前までに加盟団体となった団体は、翌年度の役員を1人以上提供する義務を負う。ただし、次に掲げる場合においては、その義務を免れる。
1. 役員選挙の立候補期間終了前までに本組織から退会したとき。
2. 役員選挙において役員候補者を輩出したものの、信任を得られなかったとき。
3. 団体の構成員が3人未満であるその他やむを得ない事情のために役員を提供することが困難であり、役員提供免除申請を行い、代表による承認を受けたとき。
2
前項において提供される役員は、各団体の執行部の構成員、各団体の代表と十分な意思疎通を行うことができる者またはそれに準ずる者でなければならない。
- 第11条(年会費)
本組織の年会費及びその納入方法は、JPDU会費納入規則の定めるところによる。
- 第12条(罰則)
1
加盟団体または会員が第9条または第10条の義務に違反したときは、JPDU議会は次に掲げるいずれかの罰則を科し、またはこれらを併科することができる。
1. 違反の是正勧告
2. 厳重注意
3. 違反の公表
2
前項の罰則を科すときは、JPDU議会において特別多数決による承認を受けなければならない。
- 第13条(会員の権利)
本組織の会員は、次に掲げる権利を有する。
1. 本組織が提供するサービスを享受する権利。
2. JPDU議会に対し、本組織の活動内容について要望を行う権利。
3. JPDU議会に対し、話し合いまたは議決その他具体的な行動を取るよう求める権利。ただし、この要望は、全加盟団体の4分の1以上の団体の同意によって、メールその他適当な方法で行われなければならない。
第3章 役員
- 第14条(役員)
1
役員選挙においては、次に掲げる役職に当たる役員を選出しなければならない。
1. 代表
2. 副代表
3. 会計
4. Equity
2
役員選挙においては、前項に掲げるもののほか、JPDU役員選挙規則に定める役職に当たる役員を選出する。
3
次の各号に掲げる役職について、当該各号に定める定数を設ける。他の役職については、定数を設けない。
1. 代表 1名
2. 副代表 2~5名
4
役員の任期は毎年4月1日から翌年3月31日を期限とする1年間とする。ただし、翌年度の役員選出が遅れたときは、JPDU議会における特別多数決による承認をもって、その任期を1ヶ月を上限として延長することができる。
5
代表は、再任することができない。その他の役員は、再任を妨げない。
- 第15条(役員の義務)
役員は、次に掲げる義務を負う。
1. 各役職の業務遂行
2. 議会及び業務で取り扱う個人情報についての秘密保持
- 第16条(役員の辞任)
役員は、業務の継続が困難その他やむを得ない事情があるときは、JPDU議会の特別多数決による承認をもって、役員を辞任することができる。
- 第17条(役員の罷免)
次に掲げる事情があるときは、JPDU議会は特別多数決による承認をもって、当該役員を罷免することができる。
1. 当該役員が第15条に定める義務に違反し、その態様が悪質であるとき。
2. 当該役員が本組織の業務遂行に著しい支障をきたしているとき。
3. 前各号に掲げるもののほか、罷免処分が相当である事情があるとJPDU議会が認めたとき。
- 第18条(役員の補充)
前二条の理由により役員が欠け、業務に支障があるときは、JPDU議会は特別多数決による承認をもって、新たな役員を補充することができる。
- 第19条(役員報酬)
役員は、報酬を受け取らずに活動するものとする。
- 第20条(会計の義務)
会計は、本組織が主催する各種イベントの予算・決算を監査しなければならない。予算・決算に不備があるときは、改善指導を行わなければならない。
第4章 議会
- 第21条(議会の構成)
1
JPDU議会は、役員選挙で選出された役員及び第10条第1項の義務を免れた加盟団体の代表者によって構成される。
2
個人会員は、本組織への入会のときに希望すれば、JPDU議会の構成員となることができる。
3
JPDU議会は、業務のために必要があるときは、参考人を招致することができる。参考人は、議会及び業務で取り扱う個人情報についての秘密保持の義務を負う。
- 第22条(議会の業務)
JPDU議会は、次に掲げる業務を行う。
1. 第3条に掲げる活動
2. 日本英語パーラメンタリーディベート界をまとめる機関として海外との折衝
3. 会員に対する決定事項の報告
4. 年度末の会計報告
- 第23条(議会事項)
次に掲げる事項については、JPDU議会の議決を経なければならない。
1. 日本英語パーラメンタリーディベート界における重要な議題
2. 第13条第3号に関連する議題
3. JPDU議会構成員の4分の1以上が議決を行うよう要求する議題
- 第24条(会議の開催方式)
1
JPDU議会において議決を必要とするときは、会議を開催する方式と、電子的な方法により表決のみを取る方式のいずれかを選択することができる。
2
電子的な方法により表決のみを取る方式を選択したときは、3日間以上の投票期間を設けなければならない。
3
電子的な方法により表決のみを取る方式が選択された場合においても、JPDU議会構成員の4分の1以上が会議を開催する方式を選択することを要求したときは、会議を開催しなければならない。
- 第25条(議会における議決)
JPDU議会は、議会の構成員の過半数の賛成をもって、第23条に定める事項を議決することができる。
- 第26条(議会における特別多数決)
1
次に掲げる事項については、JPDU議会において、各加盟団体に1票の議決権を付与し、3分の2以上の賛成を必要とする特別多数決による議決を経なければならない。このとき、複数名の役員を有する加盟団体は、自らの団体を代表する者を1名選任しなければならない。
1. 本規約の改正
2. 本規約に特に定められた事項
2
前項の場合において、JPDU議会の構成員である個人会員は議決権を有する。ただし、同一の大学等に複数名のJPDU議会の構成員である個人会員がいるときは、1つの大学等に1票の議決権が付与される。このとき、同一の大学等に所属するJPDU議会の構成員である個人会員は、自らの大学等を代表する者を1名選任しなければならない。
- 第27条(議決の履行)
JPDU議会で議決された事項は、速やかに履行されなければならない。
- 第28条(予算)
1
本組織の予算は、第2条に定める目的に合致した事業に用いられなければならない。
2
代表、副代表及び会計は、予算案及び決算を作成し、JPDU議会において特別多数決による承認を受けなければならない。
3
会員または加盟団体に対して、第11条に定める年会費以外の金銭的負担を求めるときは、JPDU議会において特別多数決による承認を受けなければならない。
4
本組織が主催する各種イベントにおいては、予算に基づいて収入の一部が本組織に納められなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
5
会計は、予算及びその使途を監査しなければならない。
6
会計は、毎年度予算及び決算を公開しなければならない。
第5章 役員選挙
- 第29条(立候補資格)
役員選挙に立候補する者は、立候補時点で会員の地位を有しなければならない。
- 第30条(投票資格)
役員選挙での投票権を得るためには、選挙開始時点で会員の地位を有しなければならない。
- 第31条(選挙管理委員会の設置)
役員選挙にあたっては、選挙管理委員会を発足させる。その運営方法は、JPDU役員選挙規則の定めるところによる。
- 第32条(選挙実施期間)
役員選挙は、役員の任期満了2ヶ月前までに開始されなければならない。
- 第33条(定数が設けられている役職の選出方法)
1
定数が設けられている役職については、10日間以上の選挙期間を経て、定数の範囲内でより多くの票を得た候補者が、当該役職の役員として信任される。
2
定数が設けられている役職に立候補する者は、立候補のときに、当該役職の役員として信任されなかった場合に、他の定数が設けられていない役職の役員として信任されることを希望することができる。
- 第34条(定数が設けられていない役職の選出方法)
定数が設けられていない役職については、10日間以上の選挙期間を経て、有効票数の過半数の信任を得たときに、当該役職の役員として信任される。
- 第35条(役職の移動・兼職の要請)
役員選挙終了後に、定数が設けられていない役職について、人数の調整が必要であると代表が判断したときは、代表は役員に役職の移動または複数の役職の兼職を要請することができる。
第6章 雑則
- 第36条(住所)
本組織の住所は、代表が所属する団体の住所とする。ただし、代表が所属する団体の住所が使用できない事情があるときは、副代表その他適当な役員の所属する団体の住所とする。
附則(2007年4月1日)
- 第1条(施行)
この規約は2007年4月1日に正式に施行される。
附則(2020年12月2日)
- 第1条(施行)
本規約は2020年12月2日から正式に施行される。
附則(2024年1月1日)
- 第1条(施行)
本規約は、2024年1月1日から施行する。